AboutMag-onについて
Mag-onエナジージェル・顆粒は
アンチドーピング商品です
「インフォームドチョイス」は、イギリスに本社を置くLGC社(Laboratory of Government Chemist.)が2007年から運営する世界最大のアンチ・ドーピング認証プログラムです。
LGC社は50年以上にわたってドーピングに関する研究や実績があり、WADA(世界ドーピング防止機構)の定める禁止表国際基準に基づき製品を分析しています。
インフォームドチョイス認証プログラムは、サプリメントの分析とともに、WADAの禁止物質リストに加え、最新情報に基づいてLGC社が分析の必要と判断した物質も加えて分析が行われることで、アスリートがより安全に製品を使用できることを保証しています。
インフォームドチョイス認証では、Mag-onの製品を毎月1回、第三者による市場から抜き取り試験が行われ、試験済みであることが保証されています。

一方でMag-on顆粒タイプでは、インフォームドスポーツの認証を受けています。
無作為抽出で検査を行うインフォームドチョイスと異なり、インフォームドスポーツは製造・製品化した段階ですべての製造バッチを分析する方法を取っています。
インフォームドスポーツの検査が行われた製品は、全ロットが分析済みのため、アスリートは分析結果を都度確認することなく、より安心して製品を利用することができます。

about
Magnesium
知られざる必須ミネラル 「マグネシウム」
マグネシウム(magnesium:
Mg)は、生体の機能維持に不可欠な生体内で4番目に多いミネラルです。約70%が骨や歯にリン酸マグネシウムの形で存在し、カルシウムとともに骨などの形成には不可欠です。筋肉(約30%)や血液(約1%)にも含まれています。
糖質代謝や脂質代謝、ミトコンドリア内のエネルギー代謝では「エネルギー通貨」であるATP(アデノシン三リン酸)の産生に関わり、たんぱく質や脂質などの生合成、遺伝子合成など生体内の300以上もの酵素反応に関与する補助因子として、重要な役割を担っています。また、細胞内液中に存在するマグネシウムイオン(Mg2+)は神経や筋肉の興奮性を抑制し、神経伝達や細胞膜の安定性、筋収縮、心拍出、ホルモン分泌などにも重要な働きをもっています。
マグネシウムの適切な摂取には、メタボリック症候群や生活習慣病、がんなどのリスクを低下させる働きのあることが知られています(※1)。

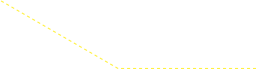

日常生活ですでに不足している?
マグネシウムの摂取と不足
マグネシウムは、生体内で合成することのできない必須ミネラルのひとつ。海草、ごま、大豆、貝類、魚類、にがり、穀類、ココア、バナナなどの食物に多く含まれています。2010年食事摂取基準(厚生労働省)によって推定平均必要量、推奨量、目安量、耐容上限量(食物以外の場合)が定められています。
マグネシウムが欠乏すると、貯蔵庫でもある骨からマグネシウムが遊離し利用されますが、食物からの摂取量が少ない場合、腸管からの吸収率が高まるため欠乏が抑制されます。マグネシウムは、シュウ酸(ほうれん草やトマト、ピーマン、ヤマイモ、青いバナナなどに多く含まれる成分)やフィチン酸(小麦、玄米などの穀物や大豆など豆類、豆腐に多い)によって吸収を阻害され、また他のミネラル(鉄、カルシウム、リン、亜鉛、ナトリウム、カリウムなど)の過剰摂取によっても吸収が阻害されます。
マグネシウムの欠乏は低カルシウム血症、筋ケイレンなどを引き起こすとされています。また、習慣的なマグネシウム欠乏は、骨粗鬆症、心疾患、糖尿病、高血圧、がんなどの生活習慣病のリスクを高めると考えられています。
一方、マグネシウムの摂取量がカルシウムの摂取量を大きく下回る場合の生活習慣病リスクとの関連も指摘されています(※2)。
平成23年国民健康・栄養調査(厚生労働省)によると、20歳以上の日本人男女におけるマグネシウム摂取量は、2010年日本人の食事摂取基準(同)に定められている推奨量を約10%~40%下回っており、女性より男性、また20歳代~40歳代で摂取不足の高い傾向が見られます。
このような摂取量不足は、穀類や海藻類などマグネシウムの豊富な食物の摂取不足が原因と考えられますが、塩分の多い食事=過剰なナトリウム摂取などによるマグネシウムの吸収阻害もマグネシウム欠乏に関与するため注意が必要です。また、汗からもマグネシウムを損失しますので、発汗量の多い場合では不足に気をつけなければなりません。
「MAG21研究会ウェブサイトより改変
マグネシウム 日本人の食事摂取基準と推定摂取量の比較(㎎/日) 対象年度 日本人の
食事摂取基準
(推奨量)
30~49歳 男性厚生労働省
国民の
推定摂取量
30~49歳 男性東京都民の
栄養状況
30~49歳 男性
(平均値)不足量 2005 370 249~265 246~250 105~124 2006 ――― 252~262 248~266 104~122 2007 ――― 250~257 238 113~132 2008 ――― 242~245 237~244 125~133 2009 ――― 246~254 238~257 113~132 2010 370 240~244 256~265 105~130 2011 ――― 231~239 238~258 112~139 2012 ――― 236~248 ――― 122~134

参考資料
「Triathlon LUMINA」より、アスリートとマグネシウムについて詳しく解説した小冊子「MgBOOK」が配布されています。
提供元:Triathlon LUMINA編集部食卓に上る「塩」の変遷と日本人のマグネシウム不足
日本人のマグネシウム不足の理由のひとつとして、食卓で使われる「塩」の変化を挙げる向きもある。かつての日本では、マグネシウムをはじめ多くの微量ミネラルを含む粗塩が使われており、塩とともにマグネシウムを摂る文化があったが、1972年(昭和47年)に塩田法が廃止されて以来、精製塩(食塩=塩化ナトリウム99%以上)が一般家庭に普及した。1997年(平成9年)には塩の専売法が廃止されたが、一般的には依然として食塩が定着している。食生活の欧米化に加え、これが日本人のマグネシウム不足を加速させる一因になったとも言われている。

参考文献
『マグネシウム 知って納得!! 健康長寿のために』(2014年、MAG21研究会発行)
マグネシウム啓発サイト「MAG21研究会」
※1 Dibabaら、2014年、Koら、2014年 ※2 Yoshiharaら、2011年、SahmounとSingh、2010
http://mag21.jp